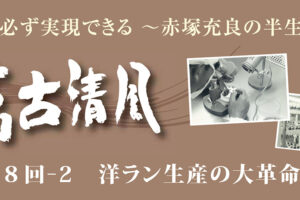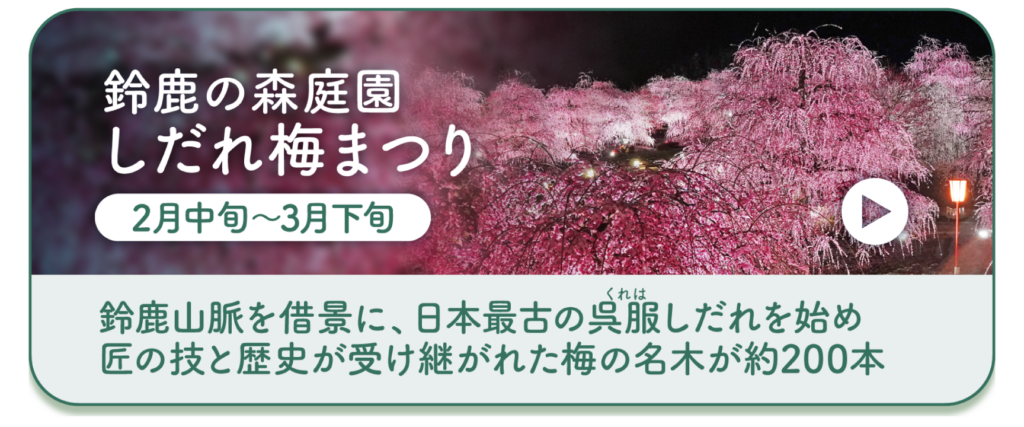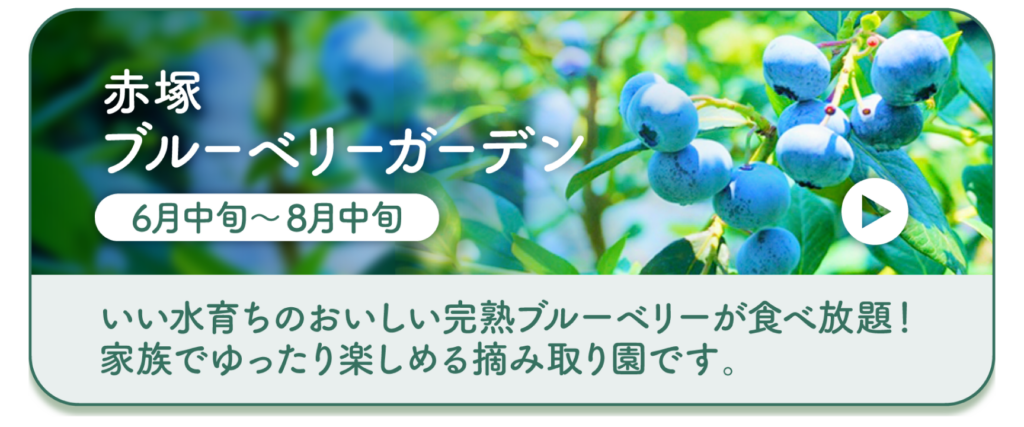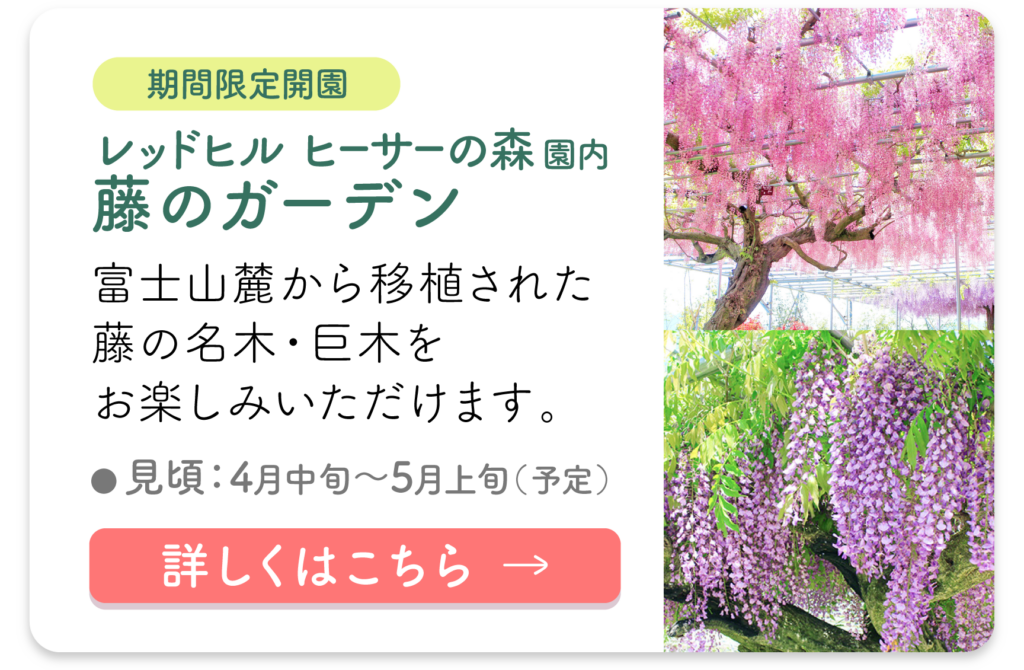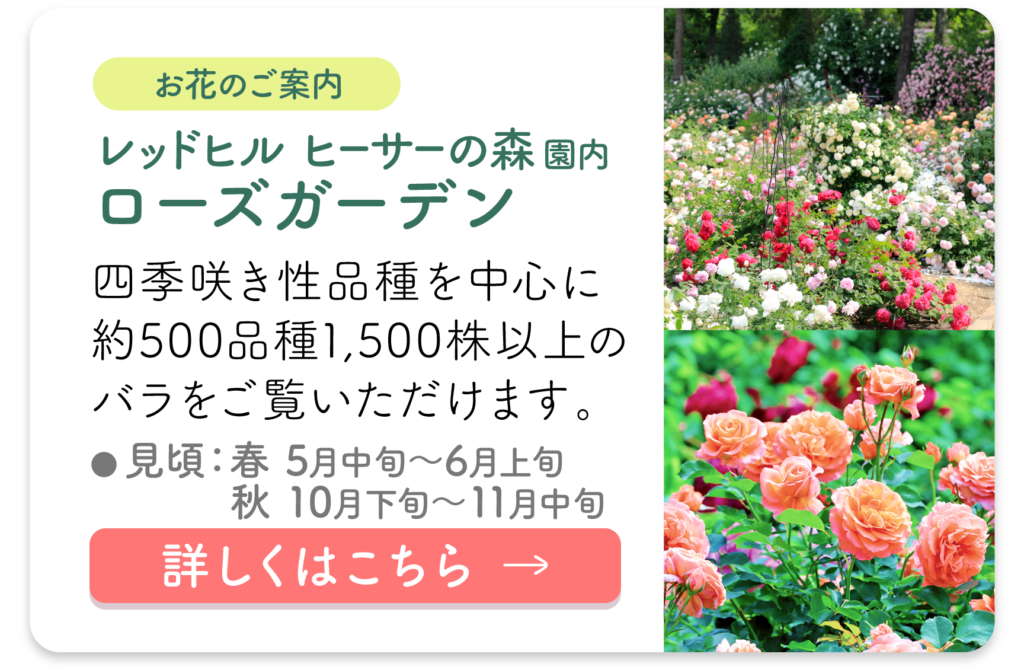洋ラン生産の大革命①
赤塚充良の間近で仕事をしてきた社員が、取り組みやエピソードをクローズアップし、その人物像に迫るコーナー『萬古清風』(ばんこのせいふう)。第8回-1は「洋ラン生産の大革命①」です。
※掲載内容は発行当時のものです。
今では手軽に楽しめる洋ラン
年末年始の園芸店は色鮮やかな鉢花で彩られます。なかでもシンビジューム、カトレ ア、コチョウラン、デンドロビュームなどの洋ランは、特に豪華で気品があるため新年の家庭を飾り、お歳暮や贈答にも利用され人気の高い鉢花です。
洋ランが鉢花としてこれほど手軽に楽しめるようになったのは、実は赤塚が大量生産と普及に努めてきたからなのです。

冬、FFCパビリオンの店内には色とりどりの洋ランが並びます
労働力の確保に力を注ぐ
昭和35年にアメリカから帰国しサツキの大量栽培を始めた赤塚は、大規模な企業的農業経営を目指しました。
ところがサツキ栽培は、苗生産や出荷の時に多くの人手を必要としますが、農閑期は仕事がありません。また屋外の仕事なので雨天や冬の寒い時は、作業ができません。
植木栽培をはじめ農業は仕事量の季節的変動が大きいので、農繁期に十分な労働力を確保しないと生産量は上がりません。特に当時は高度成長期を迎え新規就業者を募集する企業が増え、農業など不定期に多くの人手が必要な産業は、労働力の確保が大き な課題になっている時でした。
赤塚は経営の安定のために雇用の確保を重視し、一年を通じて働く人々を大勢雇いました。そして農閑期や雨天でも仕事ができるようにと考えたのが、温室やハウスを利用した施設園芸でした。
施設園芸は狭い面積でも多くの人手を必要とする集約農業です。サツキの栽培面積が広くなっても、施設園芸なら雇用した大勢の人々が働けます。
その施設で栽培する園芸植物をいろいろ探した結果、選んだのが洋ランの一種のシンビジュームでした。シンビジュームは洋ランの代表といわれ、花持ちが良くて寒さに強く家庭でも管理が容易なため、うまく栽培すれば収益の高い営利生産が可能と考えました。
苦難の連続から始まったシンビジュームの生産
昭和39年、赤塚はカリフォルニアからシンビジュームの実生苗を1,500本輸入し、栽培を始めました。
シンビジュームの苗は、大変高価な上、苗の購入から開花までに数年を要し、生産コストが非常に高くつきました。また、資金の回転が遅くなり、高価な苗を毎年カリフォルニアから買うことはできません。
買った苗をもとに自分で増やそうと試みましたが、1年間 に2~3倍にしか増やせません。シンビジュームはバルブと呼ばれる球茎を株分けして増やしますが、増殖効率は極めて低く、赤塚の目指す企業的な農業生産とはかけ離れていました。
また種子から育てた実生苗は、花の色も形もバラバラです。赤塚はできるだけ優れた個体を選抜して増やしていましたが、優良個体の大量生産は不可能でした。

アメリカ・カリフォルニアのシンビジューム農園
(文・西村富生)
>> 第8回-2 洋ラン生産の大革命②
<< 第7回 命がけの“水浸け作戦”
著者紹介
西村 富生(にしむら とみお)
㈱赤塚植物園 執行役員。生物機能開発研究所研究開発部長。学術博士。
昭和24年三重県生まれ。昭和50年三重大学大学院農学研究科終了。同年赤塚植物園入社。
入社以来、新しい園芸植物の生産に携わる一方、花木類の組織培養法を開発する。また赤塚充良のもとで水の研究を続け、FFCの開発と応用利用の研究を担当している。
(2010年1月発行 FFCテクノロジーニュース vol.9より)