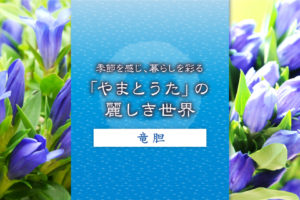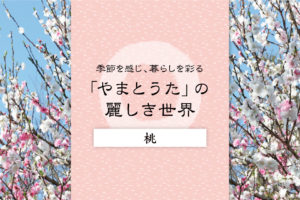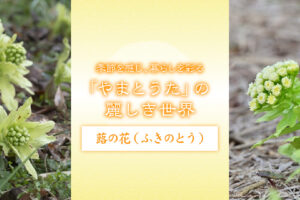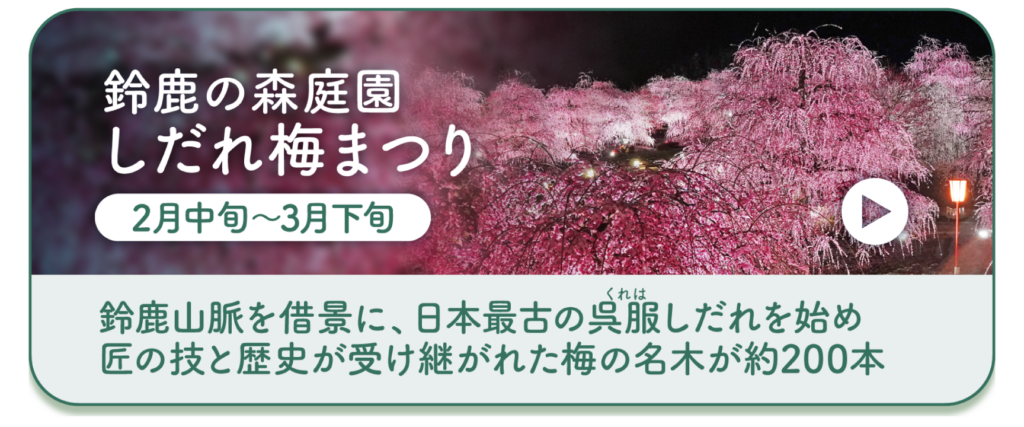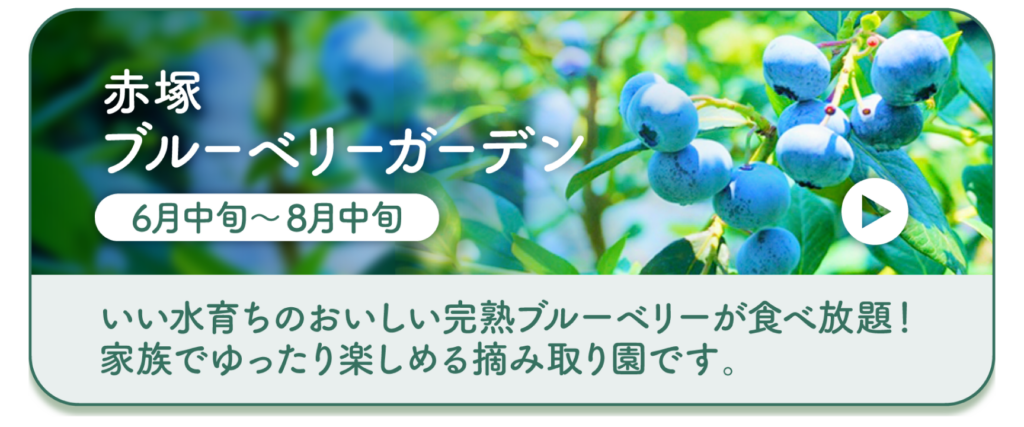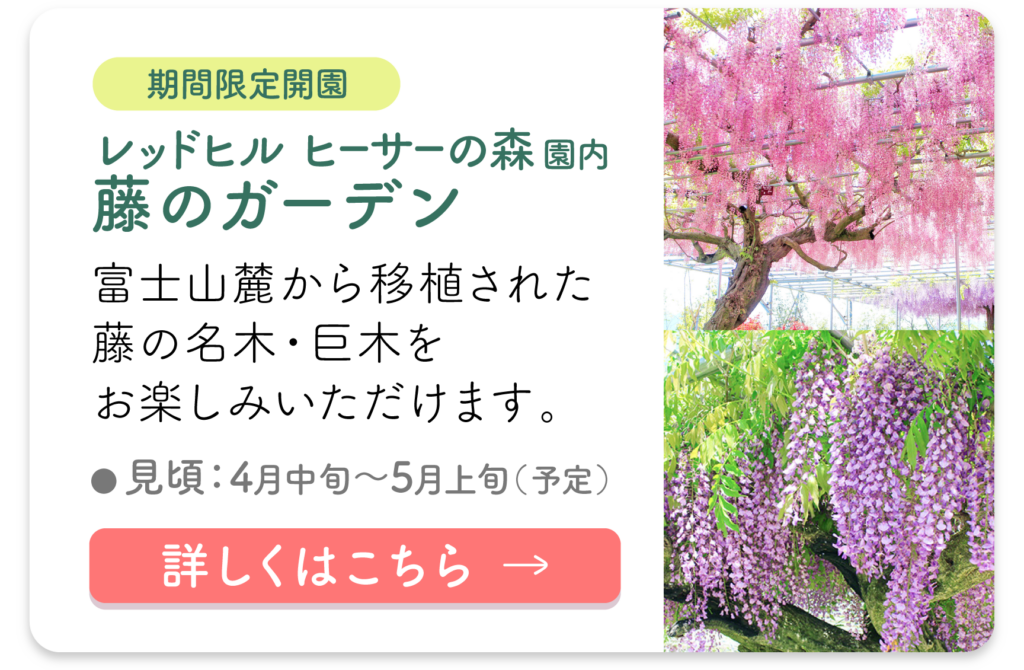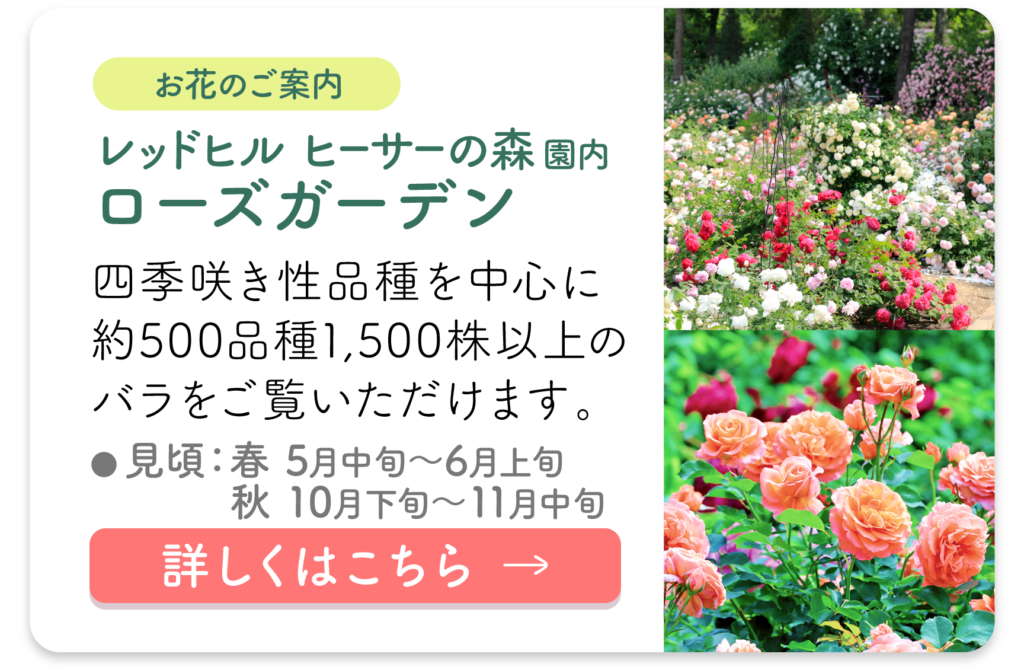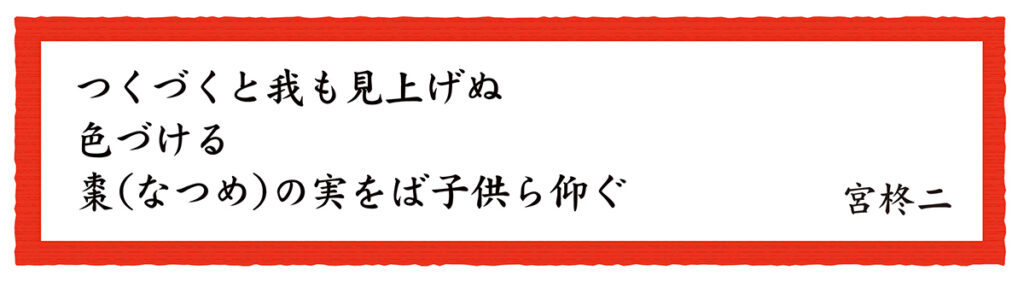
つくづくと我も見上げぬ
色づける
棗(なつめ)の実をば子供ら仰ぐ ― 宮柊二(みやしゅうじ)
【現代訳】
つくづくと味わい深く私も見上げている。こどもたちが色づいた棗(なつめ)の実を仰ぎ見ていると。
心に咲く花 2025年92回 棗(なつめ)
南ヨーロッパからアジア南西部あたりが原産だと言われる棗(なつめ)は日本最古の歌集である『万葉集』にも2首詠まれています。
中国や韓国で古くから健康にいい食材として実が利用されてきた棗。生食することができ、ほのかな甘みとフルーティーな香りが魅力的な植物です。
乾燥させたものは生薬(しょうやく)として、古くから薬膳料理などに利用されてきました。韓国のサムゲタンに利用されるほか、中国では砂糖漬が高級なお菓子として重用されています。
カリウムや鉄分、マグネシウム、ビタミン、ミネラルなどが豊富で、古来、冷え性に効くと言われ、緊張をやわらげる効能もあるとされる棗。不眠にも効果があるのではないか、と注目されています。
こうした実のイメージが強い棗ですが、5月から7月頃に淡い緑色やほのかな黄色の花を咲かせます。小さな花は、決して自己主張をする派手さはないのですが、8月から10月にかけて結実して私たちを楽しませてくれます。
掲出歌は歌集『純黄』におさめられた1首です。「つくづくと我も見上げぬ」と、宮中歌会始の選者を8回務めた新潟出身の歌人・宮柊二は詠んでいます。戦争体験を詠んだ歌でも知られる作者が眺めて飽きない棗。年を重ねて、見れば見るほど、味わい深く感じられたのかもしれません。
薬効があるのみならず、硬い材質のため、家具や茶具にも利用されてきた棗。使い込めば使い込むほど、艶が出て、魅力が増すことから、ヴァイオリンにも用いられています。
見て楽しく、食べて美味しく、用いて多様な利用価値がある棗。近所に「棗」という中華料理屋があり、伝統的な調味料にこだわった味が家族に好評なため、いつしか植物の棗にも注目するようになりました。一般に街路樹としても、庭木としても利用されています。
「長寿」「健康」「幸福な生活」などの花言葉を持つ棗。「絆」という花言葉もあるそうです。
田中章義(たなか あきよし)さん

歌人・作家。静岡市生まれ。大学在学中に「キャラメル」で第36回角川短歌賞を受賞。2001年、国連WAFUNIF親善大使に就任。國學院大學「和歌講座」講師、ふじのくに地球環境史ミュージアム客員教授も務める。『世界で1000年生きている言葉』(PHP文庫)の他、歌集『天地(あめつち)のたから』(角川学芸出版)、『野口英世の母シカ』(白水社)など著書多数。
★こちらの記事もご覧ください★
【BOSCOトーク】対談 赤塚耕一×田中章義さん